ヨーロッパ中世におけるギルドは,市場が小規模な時代において,競争を排除することでその市場を分け合い,ギルド員の共存を図る機能を持っていた。商品の生産を独占してギルドの成員である親方の間で仕事を分配し,互いの生活を保障していたのである。親方になるためには,厳しい親方資格試験が課せられたが,親方の跡継ぎ息子にはもちろん限りなく甘かった。逆にこれ以上ギルドの成員を増やせないと考えられるときには事実上合格不可能な難題が課せられ,既成の親方の利益を守った。ギルドの資格検査員も親方がつとめたから,それ自体も利権の一つであり,商品の生産を独占することで,利権もまた独占していたのである。
ギルドに対する叙述は,そのまま日本の純文学にあてはまる。日本の純文学とは,すなわち「純文学」という品質保証の商品を独占するギルドである。芥川賞を初めとする文学賞は,親方資格試験であり,その選考委員となることはギルド員として利権を握ることである。これによって自分たちが独占する商品の品質を自分たちが都合のいいようにコントロールすることが可能となる。また,晴れて文壇(ギルド)の一員と認められれば,そこには生活を保障する様々な利権が存在する。大学教員の口や,新聞・雑誌での書評・エッセイなどはギルドが管理する利権であり,ギルド員はその分け前に預かることができる。世間的権威に比して市場が決して大きいとは言えない純文学は,利権を独占することによってギルド員(純文学作家)の共存を図ってきたと言えるだろう。
「大衆文学」と「純文学」が人々の意識の上でも,あるいは内容の面でも住み分けられていた戦後の一時期までは,ギルドとしての日本の純文学は有効に機能していたと考えられる。しかし,今やその機能は明らかに失われつつある。「純文学」ブランドに対する人々の信頼は薄れ,「純文学」作品はますます売れなくなり,ギルドとしての純文学自体が危機に瀕しているのだ。
このような惨状は,いかにしてもたらされたのか。
ギルドの本質は二重の独占である。人々が求める「商品価値」を独占供給できてこそ,ギルドはその利益の分配を独占する利権集団として機能する。では,その独占供給が崩壊した場合はどうなるのか。すなわち,日本で純文学が独占的に供給していたはずの商品の価値とおなじものが,純文学以外のどこかから提供されたならば。
独占提供の崩壊は,すなわち利権独占の崩壊につながる。
ここでわれわれは,純文学が極めて困難な状況に直面していることを知る。純文学作品の買い手は,「純文学」という品質保証を信頼して商品を購入する。そしてその品質保証とは,「わたくしども純文学が提供する商品は,他のいかなるジャンルの作品よりもこと文学性に関してはたこうございます。駆け出しの芥川賞作品といえども,その点に関しては,安心してお買いなさいまし」というものである。日本の純文学にとってみれば,自分たちが文学賞で「純文学」という品質保証を与えた作品は,他のどんなジャンルのどんな作品と比較しても,こと「文学性」で劣っていてはいけないのである。そうでなければ,自分たちのブランド価値が傷つき,独占が崩壊するからである。
もちろん,そんなことは今や不可能である。既に出現期の村上春樹は,当時日本ではSF作家とみなされていたアメリカの現代作家カートヴォネガットの影響を濃厚すぎるくらい濃厚に受けていたし,出現期の吉本ばななには,明らかに大島弓子などの少女マンガの影響があった(姉がマンガ家で,本人も当初はマンガ家を目指していたというのは有名な話)。そして現在ではマンガ作品やアニメ作品の影響を受けたりマンガ作品をパクった作品が次々と文学賞を受賞するようになっている。
一方でここ10年来「純文学」として発表された幾多の作品のうち,「文学性」においてマンガである岡崎京子の『リバーズエッジ』に互することが出来たものは,いったいどれくらいあったのだろうか。
数年前,書評誌「ダ・ヴィンチ」で,「芥川賞をとらせたいマンガ」という特集がなされた。現下の状況で「芥川賞をとらせたい」はないと思うが,この辺に,「純文学」ブランドを信奉し,その影響下にある業界人は,まだまだ多いんだろうな,ということを思ってしまう。しかし,多くの消費者にとって「純文学」という商標は,商品を選択する上において,今やほとんど意味をなさない。本屋の店頭でも,「純文学」作品が,特別扱いされているわけではもはやない(むしろ差別されている)。消費者が文学性の高い作品を欲すれば,マンガ作品の中からでもいくらでも選択出来る現状が既に存在しているのである。
もともと市場が小さい純文学が,こうしてブランド価値を失っていく時,純文学は,仲間内で融通しあい,現在までかろうじて保持してきた,大学講師のポストや,新聞・雑誌のエッセイなど,様々な利権をますます失っていくことになるだろう。そしてかつてなら純文学を志していたような才能は,ますます他分野へと流出し,純文学には二流の才能しか集まらなくなり,それはさらなる衰退への悪循環を導くことになるだろう。
このような危機的状況に対して純文学はどのように対応しようとするだろうか。
一つ考えられるのは,「異物」を取り込むことによって取扱品目を広げ,生き残りを図ろうとする方向である。「性と暴力」の作家,花村萬月の芥川賞受賞は,このような文脈で考えると了解出来る。「これも純文学なんだ」と取り込むことで,「性と暴力」を純文学ギルドの管理下に置き,他のギルド員もその分野に進出できるようにする。『日蝕』,『中陰の月』と続く「神秘主義系」作品の受賞も同様であろう。
今一つは,縮小するパイを既成のギルド員で分け合うために,自分たちを脅かす存在を排除することである。
2001年,津原泰水の『ペニス』が出版された。津原泰水は「津原やすみ」として長らく少女小説の分野で活躍していた。一般向けに発表された最初の作品である『妖都』は,ホラー小説として世に迎えられた。次に出版された『蘆屋家の崩壊』は怪奇幻想短編集と銘うたれたが,年末恒例の「このミステリがすごい」でベスト20にランクインしたように,ミステリ小説の形式をとっていた。このような出自と経歴を持つ津原泰水がものにした『ペニス』は,当初「小説推理」誌に連載作品として発表されたが,しかしその作品内容において,「純文学」としか言いようのないものだった。もともとその文章力とイメージ喚起力を高く評価されていた津原泰水は,『ペニス』において,文章表現の可能性に果敢に挑戦し,映像化不可能な,言葉の真の意味においてまさに「文芸」としか言いようのない傑作を世に送り出したのである。出版前から既に「ダ・ヴィンチ」で著者インタビューが組まれ,朝日新聞の書評でも紹介され,純文学ギルド外の何人かの書評家からも絶賛された『ペニス』は,21世紀最初の年に,最も話題となった「純文学」作品であり,村上春樹や村上龍や高橋源一郎や,ひょっとすると中上健次の諸作品よりも,純文学らしい純文学だった。
しかし,純文学ギルドは『ペニス』を完全なる沈黙で迎えた。「あれは純文学ではない」という類の批判すら一切無かった。
マンガ作品に対しては,マンガ表現と文章表現は別であるからとかろうじて言い訳することが出来るかも知れない。本来の純文学から外れたところにあった花村萬月は,純文学に取り込んで,むしろ純文学の取扱品目の多様化に活用できたかもしれない。しかし『ペニス』と津原泰水の存在は,純文学ギルドにとって災いである。純文学とは異なる分野で活躍してきた作家によって,ミステリ専門誌である「小説推理」誌に発表され,「純文学」ブランドの商品保障がどこにもついていないにもかかわらず,純文学としか呼びようのない傑作,それは「独占」によって利益を分配してきたギルドとしての純文学の存在価値を木っ端微塵に打ち砕くものであるからだ。
しかし,このようにして純文学ギルドが,既成のギルド員だけの生き残りを謀っている間に,2001年12月にはもう一つの傑作,古川日出男の『アラビアの夜の種族』が発表された。両作品を核に「幻想文学」というブランドを,純文学に代わって成立させようという動きも胎動しはじめた。あくまで文章表現を指向する才能には,純文学に代わる,しかも純文学よりも市場性の高い,新たな受け皿の用意が始まったのである。
純文学というギルドによって無視された『ペニス』は,それ故に純文学というギルドの死亡証明書として後世の文学史家に記されることになるだろう。
 へ戻る
へ戻る
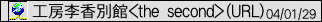 トップへ戻る
トップへ戻る